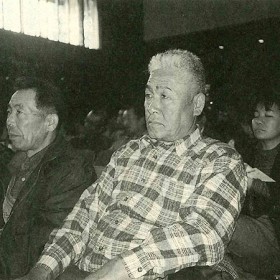欠品がある。
「すみません。今日は大根が予定より少なくて、注文8本のところ5本でお願いします」
「エエーッ!今日はおでんにしようと思ってたのにぃ~」
「じゃあ、私はなくてもいいわよ」「ごめんねえ」
そんな会話をしながら人参を量り(秤もグループで用意する)、分けていく。
「すみません。堀田信宏さんが無農薬で作ったカブ。結構獲れたんで、あと3束お願いできませんか」……いいカブね、と4人から手が上がる。

共同購入の様子
メンバーに共働き世帯があれば、誰かが夜まで保管してあげる。そのために冷蔵庫を用意したグループもあった。当番がそれぞれの購入金額を計算して、翌週までに集金する。共同購入とはかくも面倒なものだった。
それでもステーションは増えていった。この真髄は何だったのか。
当時はまだ有機野菜が簡単に手に入る時代ではなかったから。それは言える。藤田代表がいつも言う「安全なだけでなく、何より美味しかったから」。それもあろう。東京集会や産地訪問などを通じて生産者と顔なじみになることで醸成される「食への安心」も、持続力を高めたと思う。「私たちが支えなきゃ」という心も芽生えたりする。まさに「顔の見える関係」の核心が共同購入には表現されていた。
加えて、配送員の僕が見たのは、食材の共同購入だけでなく、様々な形で助け合う光景だった。用事が出来れば子供を預け合う、子育ての悩みを相談し合う、姑への愚痴なども言い合う。病気になれば諸事手伝ったり、モノを分け合ったり、一緒に食事をしたり、時には学校への陳情作戦を練ったり。
仲間がいるという安心感。それは都会に新しく生まれた、小さなコミュニティだった。男にはとてもできないワザだ……と、20代の若き配送員は思ったものだった。
85年から大地を守る会は個人宅配サービスを導入する。その背景はいずれ1話にまとめたいと思うが、宅配を始めると同時に、地区連絡会の結成や交流活動の充実(交流局の設置)などに取り組んだ。僕らは本能的に「輪」の重要性を悟っていたと思う。
個が孤となり、買い物難民などという言葉が生まれる時代。いま改めて、小さなコミュニティづくりの応援も見直してみてはどうだろうか。
そしてもうひとつ。僕が入社(1982年)した頃から、新しい兆候が表れていたことも付記しておきたい。
ある日の配送での出来事。一人のお母さんが5歳くらいのお嬢ちゃんの手を引いてきて、「このお兄さん(僕のこと)に、お礼を言いなさい」と言ったのだった。えっ??僕は何もしてないけど……。そして堰を切ったように語り始めた。
「大地に入って3ヶ月で、こんなにきれいな顔になったのよ」…今にも泣きそうだった。
アトピー性皮膚炎という新しい言葉が生まれていた。そして無農薬・無添加の食材に切り替えて改善したという事例も増えつつあった。何を隠そう、僕自身、入社する1年前に大地を守る会に入会していて、そのきっかけは娘のアトピーだった。我が家もまったく同じような経験をしていたので、そのお母さんの心情は手に取るように理解できた。僕もちょっとウルッときて、その子と握手した。本当に嬉しそうだった。彼女も今は母親だろうか。
もとより、大地を守る会はアトピー対策の団体ではない。個人差のある話でもあり、効果を謳うこともない。しかしよく見渡せば、アトピーの症状を持つ子を抱える母親の姿が、すでにそこかしこに見えた。
「子供たちの未来のために、美しい大地ときれいな海を取り戻そう」
-大地を守る会のスローガンだが、みんな、子供たちの未来のために、頑張っていた。
このミッションを忘れてはならない。そういう宿命を背負った組織なのだ。