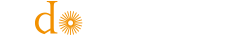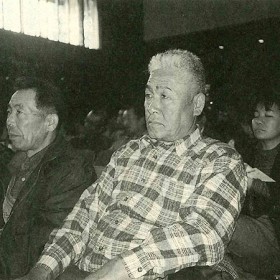子供たちのために、頑張ってより良い学校給食を実現させよう。また給食は教育の一環と位置づけられたものである。センター給食に代表される現場の合理化にも反対していこう。その共通認識が教職員(日教組)と調理師(自治労)の間に成立し、日本消費者連盟も参画して、全国学校給食を考える会も合わせ、この運動は「4者共闘」と呼ばれた。それはけっこう画期的な運動だった。大地を守る会は常にその中心的役割を果たしてきた。
前回 【第9話】学校給食に無農薬野菜を! はこちら
しかし、こと食材の供給という具体的なミッションは思うように進まなかった。前回書いた「運動を諦めさせるに充分な現実」が立ちはだかっていた。
たとえばこんなオーダーが入る。同じサイズのミカン825個とか、ブドウ2,864粒とか。生徒たちに公平に分けなければならないという話である。そこで最初は生真面目に数えて正確に納品したが、それは素人のやる仕事だった。傷んだブドウ粒があって、激しいクレームとなった。次に重量や歩留まりを計算して、多めに納品するようにした。当然ロス分はこちらがかぶることになる。
その時の入荷状況次第では、共同購入を欠品にしてでも学校に届けた。あえて儲けのない場所に、会員に頭を下げながら。
そしてもう一つの難敵に気づかされる。地域の学校に納入していた八百屋さんである。僕らは彼らの既得権を侵していた。
学校給食の食材調達には強大な既成システムが存在していた。文部省管轄下に全国学校給食会という組織があって、各都道府県から自治体へと下部組織化され、給食費や補助金の運用=食材の調達には納入業者が指定され、栄養士が自由に相手を選べるものではなかったのだ。給食会の会長は教育長が兼任していた。
当時20校くらいに広がっていた大地を守る会の食材供給は、実はほとんど栄養士さんの裁量範囲内の努力に依存していた。たとえば落合第一小学校の革命的給食は、西山千代子さんという強烈なカリスマ栄養士の存在によって成り立っていたのだ。無農薬野菜を使いたいと言えば、まず返ってくるのは「圧力」という壁である。
新たな議論が始まる。大地を守る会の物流センター(当時は調布市深大寺)から東京・千葉・埼玉にまたがる学校に、苦労しながら配達することの是非と解決策について。
突破口を開いたのは、自分たちだけで完結させない、“社会を巻き込む”という発想だった。ひと言で言えば「だったら地元の八百屋さんを通せばいいじゃん」というものだ。
学校から大地を守る会にオーダーが入る。大地を守る会はその野菜を地元の納品業者である八百屋さんに届ける。大地を守る会に欠品のリスクがあれば、八百屋さんが市場から調達して納品する。この妥協は許してもらおう。八百屋さんは一校に限らずエリア内の学校に営業が可能になり、多めに仕入れておいてお店で売ることも可能になる。そう、町の八百屋さんでも有機野菜が売られるのだ、普通に。そうやってみんな少しずつ楽になって、win‐winの関係が築けるのではないか。
この構想は東京都品川区で実現した。今でもお付き合いのある島田青果さんが先陣を切って展開され、「品川方式」と呼ばれるまでになり、多い時には130校にまで無農薬野菜を扱う学校が増えた。
現実のシステムや利害関係者、つまり社会を巻き込む(仲間にする)ことによって、現実的課題を前進させる。そんな運動手法を、学校給食という現場を抱える人たちとともに、大地を守る会は獲得していったのである。「農薬の危険性を百万べん叫ぶより無農薬の大根一本を」と叫んだ精神を、ひとつの組織論として結実させた事件だったと言える。
しかしこの方式での学校給食運動は、持続させることができなかった。現場は、あまりにも個人の力に依存していた。栄養士には定年や転勤がある。熱心だった父母も子供の卒業とともに関係が切れる。後継者を“また一から”育てるより早く、センター化は進展した。品川区でも、支援してくれていた議員(たしか公明党の方だった)の退陣とともに失速した。大地を守る会も、儲からない=持続困難な事業に苦戦していた。労働組合も変遷した。
しかしそれでも、「より良い学校給食を」の旗は降ろさない。したたかに、現実に対応しながら、ミッションを持続させる。そうでなかったら、やった意味、やり続ける意味がなくなってしまう。大地を守る会の存在意義を、僕らは改めて考えなければならないと思う。
言葉を変えるなら、新しい運動手法が求められている、ということかもしれない。子供たちの未来のために、問い続けよう。