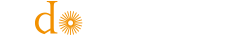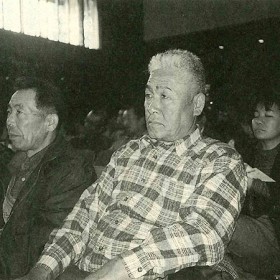僕が大地を守る会(当時は㈱大地)に入社したのが1982年11月。
その頃もまだ、鮮魚取り扱い論争はくすぶっていた。
共同購入の配送で、今でも忘れない会員Aさんとの会話がある。
静岡・内浦漁協との産直が始まり、「ワンパック魚」と称した鮮魚セット(揚がった魚から組み合わせる産地お任せセット)を届けた時のことだ。
「この魚の産地はどこ?」(知ってて注文したくせに…)
「静岡の内浦漁協、沼津の南で…」
説明を遮るようにAさんの質問が飛んできた。
「じゃあ同じ場所で獲れた魚が魚屋さんで売られていたら、おんなじ魚よね?」
「まあ、そうですかね」
「だったら、わざわざ大地(を守る会)から買う意味ないわよね?」
・・・僕はたじろぎ、答えに窮したが、誰も助けてくれない。開き直って答えた。
「おんなじ魚だったら、大地から買ってくださいよ」
・・・想定外の返答だったのか、開いた口が塞がらない状態のAさんに、僕は苦し紛れの説明で逃げを打った。
「大地から買ってくれたら、皆さんのお金が、おんなじ産地でも海を守ろうと頑張ってくれる漁業者のほうに回ります。僕もそういう仕事に打ち込むことができます」
「同じもんなら」とはヌケヌケと言えたものだが、近海漁業の鮮魚を扱うとは、そういうことだ。新人の突然の回答としてはよくできたと、実は今でも思っている。
漁師たちの暮らしを良くすることと海の環境を守ることが得てしてリンクしない実態を見てきた漁村育ちの身(漁協職員の子)として、切ない夢のようなものが潜んでいたのかもしれない。
Aさんが魚を好きだったからこそ、あえてオーダーし、成り立った会話である。
幸いにAさんはその後、「ワンパック魚」を継続して注文してくれるようになった。
自慢話に聞こえるかもしれないけど、こんな話は僕だけのものではなくて、当時、配送員はそれぞれの思いと言葉で、“魚を扱う意味”をしどろもどろに語っていた。
そして必然的に水産物の産地との交流も活発になっていった。静岡、青森、宮城、北海道、福岡、高知、鳥取、神奈川……
交流を深めるうちに、実感することになる - これは「同じもん」ではない。
同じ漁場であっても、二宮さんの牡蠣は違う、岩崎さんのシラスは違う、成清さんの海苔は違う。同じ無添加でも遠藤さんの練り物は違う、島源の干物は違う……。
それは人と人の交流から新たな「価値」が生まれていった、ということではないだろうか。
生業(なりわい)と消費が、“海を守りたい”という連帯意識でつながった時、同じ金額でも、その価値は違ってくる。ただの対価でなく未来への保険も入ってる、みたいな。
いのちあるお金の循環……そんな自立した関係(経済)による未来保障システムを、僕らは「魚の取り扱い」から夢見たのだ。その海に原発など不要である。
このテーマにチャレンジした事業的意味を、僕は死ぬまで考え続けたいと思う。
「“考える素材”としての魚」の提起から2年。
1984年3月に開催された「大地を守る東京集会」では、海がテーマに設定された。
付けられたタイトルが、「大地そして海へ」。
そこで初めて、海からの生産者がパネラーとして登壇した。宮城・遠藤蒲鉾店の遠藤栄治さんが、蒲鉾づくりから原料の大切さを語れば、同じく宮城・奥松島の二宮義政さんは漁協婦人部が10年の歳月をかけて合成洗剤を追放した道のりを報告した。
ひとり芝居で全国を行脚していた愚安亭遊佐(本名:松崎勇蔵)さんが、原発という国策で“海が盗られていく”惨状を訴えたのも、参加者の心をとらえた。
海と陸はつながっている。海は陸の矛盾を引き受けている。
環境を守り、食の安全を確保するために、大地(農業)と海(漁業)はつながらなければならない。ともに守り合える世界を、一歩ずつ築いていこう。「食べる」とは、それをつなげ、循環させる営みに他ならない。子供たちの未来のために-
なかなかに熱い東京集会だった。
僕は入社2年目でこの2日間の総合司会をやらされたのだが、気合が入り過ぎてか、最後に感極まって泣いてしまったのだった。