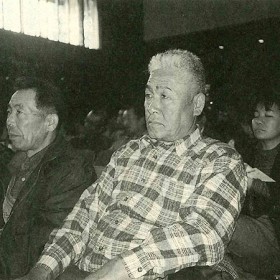時は1986年。まだ寒い時期だったと思う(記憶が定かでない)。
ワクワクするような話が舞い込んできた。
鹿児島県徳之島でバナナを栽培している青年がいる(正確には地元農家をまとめようとしている都会からの移住者)。しかも無農薬栽培に挑み、産直ルートに乗せることで島おこしをやりたいと意気込んでいる。青年の名前は奥田隆一さんと言った。
国産バナナは生きていたのだ。会いに行こう!
当時(今も本質的には変わってないと思うが)、バナナといえば、我々の間では象徴的な食べもの(作物)だった。
1963年にバナナの輸入が自由化されてから、市場はそれまでの台湾産や南米産を駆逐するようにフィリピン産の輸入が急激に増えていった。
フィリピン国が輸出に力を入れたのではない。多国籍企業が、日本市場を狙ってフィリピン・ミンダナオ島にバナナ・プランテーションを開いていったのだ。
ミンダナオ島が選ばれたのは、一年中温かく雨も降る気候(バナナは通年収穫される)に加えて、バナナにとって大敵の台風が来ないからである。
多国籍企業は、地主から農地を借りるという手法で農園を拡大していった。自給ベースだった畑が日本向けバナナ栽培地に変わっていった。自給的暮らしをしていた小作人はプランテーションの労働者となり、わずかな賃金で食べものを“買うしかない”立場となった。
輸出用バナナには、見栄えと病害虫対策のため大量の農薬が使われた。労働者(元農民)は、農薬の危険性を知らされないまま上半身裸で散布作業に従事し、体を壊した者は使い捨てにされた。
農薬と化学肥料で痩せていった土地は、生産性が合わなくなると地主に返された。地主に残ったのはお金と不毛の土地である。労働者は都市(スラム)に流れていくしかなかった。
バナナは完熟では輸出できないため、青い状態で出荷される。ひっきょう味も落ちる。いつの頃からか“バナナの叩き売り”(腐らないうちに売りさばく)光景も見られなくなった。
そして消費者運動の間で「フィリピン・バナナは農薬まみれ」と言われるようになり、拒否する人が増えていくのだが、関心を持った人は、その奥に、上記のような問題が横たわっていることにも気づかされることになる。
多国籍企業が巨大化してゆく一方で、土地が収奪され農民の貧困化が進む構造に、私たち日本人は手を貸しているのではないか。安くなったバナナを頬張りながら-
そんな世界を明解に描き出したのが、人類学者・鶴見良行さんによる『バナナと日本人』(岩波新書)だった。出版されたのは1982年。
実はその2年前、大地を守る会理事(当時)の加藤保明がミンダナオ島のバナナ・プランテーションを視察している。彼もまた、自分が撮ってきたスライド写真を持って、ステーションを回っては“フィリピン・バナナと私たち”を語っていた。
その間にも、国産バナナは人知れず消えていった。そんな時代だった。
解説が長くなってしまったけど、そして1986年、である。
無農薬・国産バナナで島おこしをやりたい、という青年が彗星のごとく登場したのだ。
他の有機農業団体にも声をかけて、みんなで会いに行こう。
しかも、せっかくだから徳之島だけでなく、貴重なサンゴ礁が埋め立てられようとしている石垣島・白保の人たちとも交流したい。核のゴミ捨て場計画が持ち上がっている奄美・加計呂麻島も回りたい。そして現地の運動を支援するだけでなく、環境を守りながらどう暮らしを立て直していくか、一緒に語り合いたい。
いっそのこと、大型客船をチャーターして、いろんな団体に参加を呼びかけてはどうか(「ピース・ボート」という先行モデルも生まれていた)。
食だけでなく、環境、医療、教育、福祉、平和、反原発……様々な市民団体が垣根を越えて交流しよう、船内シンポジウムもやったりして。よし、“いのち・自然・暮らし”を共通キーワードとして、もうひとつの生活を創るネットワーカーズの船出!といこうではないか。
最初の仕掛け人は「徳島暮らしをよくする会」代表の西川栄郎さんで、大地を守る会理事の徳江倫明(いずれも当時)が呼応し、共催団体は一気に膨れ上がっていった。
「赤字になったらどうするんだ」という慎重派の声をモロともしない気運が生まれていた。みんな若く、新しいつながりを求めていたのだ。
つけられた船の名は「ばななぼうと」。
「徳島暮らしをよくする会」「大地を守る会」「全国ポラン広場」「日本リサイクル運動市民の会」「県民生協やまゆり」などが集まって実行委員会が結成され、企画が形づくられていき、これから広く参加を呼びかけようとした時、4月26日、ソ連・チェルノブイリ原発が爆発した。