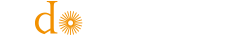料理にひと振りするだけで、尖りのないさわやかさを添えてくれる。台所の名脇役、庄分酢(福岡県大川市)の酢は、どのように醸されるのでしょう。創業300余年。伝統の酢造りをつなぐ人たちを訪ねます。
昼夜が等しいお彼岸のころに
豊かな水をたたえる筑後川の岸辺に、菜の花が揺れています。関東では春の訪れが足踏みしていた3月の半ば、ここ福岡県大川市ではやわらかな光が差して、空気が緩みはじめていました。
私たち人間が過ごしやすいと感じるお彼岸のころは、暑くもなく、寒くもなく、気温が安定する時期。庄分酢の酢造りの原点、「有機玄米くろ酢」の仕込みは、古くから年2回、春と秋のお彼岸前後に行われてきました。
酢の醸造方法には大きく分けて「全面発酵」と「静置発酵」の2通りがあります。酢造りに活躍する酢酸菌は、空気に触れているところでしか働きません。この菌の活動を促すため、機械で空気を送り込むのが「全面発酵」で、いわばスピード製造。対して「静置発酵」は、自然な発酵を待つスローな造り方です。庄分酢では後者の方法を続けています。
そして「有機玄米くろ酢」の場合、原料は、玄米、米麹、水だけ。
地面に埋まって並ぶかめに、この3つを入れて仕込みます。時代を越えて受け継がれてきた、古式ゆかしい酢造りを見せていただきました。

玄米を蒸すくろ酢の仕込み
「この香りがすると、今年も春が来たなって感じがしますね」と、十四代・髙橋一精(たかはしかずきよ)さん(69歳)。蒸気がもくもくと立ち上る蒸し釜に、やさしい眼差しを向けます。
米から酒ができるように、酒から造られる酢もまた、米からできます。玄米を蒸す香りが、庄分酢の春の風物詩です。
釜の木蓋を開けると、米は黄金色に蒸し上がっていました。あつあつの中をのぞき込む酢職人、福山寛(ふくやまゆたか)さん(50歳)。指でつぶしたり、手のひらで押したり。真剣な面持ちで蒸し具合を見ます。原料3つのみで造る酢は、この蒸し上がりが出来を左右するからです。
「指でぎゅっとつぶれるくらいが目安です。粒が割れているのもありますが、この状態が理想。割れているくらいの方が、麹菌の酵素が入っていきやすいんです」
酢は、「米から糖」「糖から酒」「酒から酢」という3段階の発酵ででき上がります。初期の発酵では、麹菌が米を糖に変えますが、玄米が表面をかたく閉ざしたままでは麹菌が入っていけません。そのため、洗米の際には磨くようにこすり合わせ、蒸し上がりの粒は細かくほぐし、米の段階から手をかけてあげるのです。


かめの中に仕込みの水、地元の麹屋さんから届いた米麹、蒸し米を入れ終えたら、均一に撹拌します。
そして、仕上げに施すのが「振り麹」。振り麹とは、少し残しておいた米麹を、浮かべていく作業です。このときの酢は生まれたての赤ちゃんの状態。米麹が浮くと麹菌が表面で盾となり、酢の赤ちゃんを雑菌から守ってくれるのです。
作業が終わったら、和紙の蓋をかぶせ、縄で二重に縛ります。そして酢職人たちは筆を取り、今日の日付と酢の名前を記しました。筆跡がサインの代わりとなります。






菌を見守る手入れの仕事
かめの中では、このあと何が起こるのでしょう。福山さんが話します。
「3日間は蓋を開けません。3日経って蓋を開けたとき、うまくいってると、麹菌の菌膜がふわーっと繭のように張っています。あとはかめの中で菌が働いてくれますので、私たちはそれを見守るだけ。手入れでカバーしながらですね」
福山さんがいう手入れとは、酢を造る菌の手伝い。庄分酢の酢の発酵にとって良い菌と雑菌を見分けて、良い菌を優勢に導いていく作業です。良い菌を見分けるとはどういうことでしょうか。
仕込みから2週間たったころ、かめの中で酒のでき方がゆるくなるとアルコール発酵は後半となり、米が沈んできます。これが酢酸発酵、つまり酒から酢に変わりはじめるサインです。
この状態になったら、蔵で仕込んでいる酢酸菌の出番。元菌と呼ばれるこの菌を一つのかめに移植します。蔵に棲み付くとされる蔵付き菌によって、酢から酢へと長年つながれてきた菌です。
元菌を移植してしばらくすると、かめの中の表面に酢酸菌の膜が蜘蛛の巣のように張ります。これが良い菌の膜だと判断したら、ほかのかめにも移します。
「良い菌は白っぽい、黄色っぽい色をしていたり、香りが甘かったりします。良い菌は全面に広げ、ちょっと違うなというのがあったら、取り除くというのが私たちの手入れですね。そっくりの菌に騙されて、数日たって、やっぱり良くなかった、ということもあります。生き物なんで思い通りにはいきません」
このようにして職人たちは菌の表情を読み、菌を助けながら、およそ3カ月の発酵を見守ります。そのあと、場所を移して半年以上熟成。出荷されるまでには、1年以上の歳月がかかります。

家伝に残された酢造りの思い
目に見えない菌との二人三脚で造る酢。見た目には分からなくても、確かな味が受け継がれてきました。
「昔は醤油屋さんや味噌屋さんのように、町に1軒、お酢屋さんがあったんですよ。それが、親父から私に代替わりするころに次々廃業していきました。しかし、うちには蔵がある、かめがある、伝わってきた方法があると、自分たちを見直したんです」と、髙橋さんが振り返ります。
高度経済成長の波に日本が沸き返り、大量生産が主流となった時代でした。しかし、速く、たくさん造る方法ではなく、「価値あるものは手の中にある」と、先祖伝来の方法を貫いたといいます。
創業は江戸の昔、1711年。庄分酢には、一子相伝、相続人のみに受け継がれる酢造りを綴った家伝が残されています。木箱に納められた巻物には、今に続く「有機玄米くろ酢」の造り方が記されています。
「前文に〝相続人よりほか、いかなる場合といえども見すること無用のものなり〞と書いてあります。だれにも見せちゃならんということなんです。想像するに、当時は温度計もエアコンもない時代。しかも菌は目に見えないんですよ。真っ暗闇で仕事をしているようなものでしょう。やっと見つけた方法を、子孫に託す思いがあったんでしょうね」
髙橋さんも家伝にならって試行錯誤の酢造りを行ってきました。そしてこの先、息子の清太朗さん(37歳)にも、引き継がれていきます。
子々孫々に手渡されてきた庄分酢の酢造り。バトンをつないできた人々のおかげで、今のおいしさがあると知りました。
お酢を変えると料理が変わります。和洋問わず、和え物、炒め物、煮物に足してみてください。酸味だけではない、時が醸した深いこくと香りが、家庭料理の味を豊かにしてくれることでしょう。


大地を守る会の酢はこちら
※該当商品の取り扱いが無い場合があります。