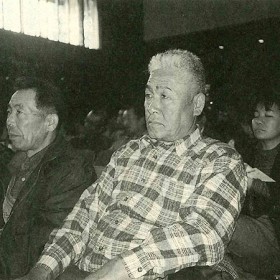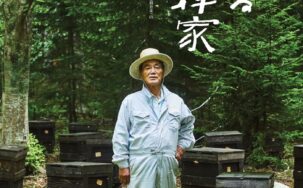前回までの連載「走り続けて40年、大地を守る会の原点をたどる」はこちら
さてここからは、大地を守る会の哲学というか組織論や企業文化が形成されていく上で、エポックメーキングとなったいくつかの運動(movement)や出来事(event)を取り上げていきたいのだが、
その前に片づけておかなければならない歴史がある。
どういう組織として生きていくのかという土台の部分について。
「ヒストリー」と銘打ったからには、スルーできない話である。
創業時の極貧状態については初めにも触れたが、設立2年を経て、年間売り上げが2千万を超えたあたりで、この議論は発生した。
仲間が集まって始めた「活動」は、すでに専従スタッフを抱える「事業」となっていて、藤本や藤田は無給でも奥さんの稼ぎで何とかなっていたものの、
スタッフには給料を払わなければならない。
社会保険にも加入させたい。
事務所や倉庫には設備投資が必要だ。
トラックも買わなくちゃ……
しかし社会的信用のない任意団体には、銀行は見向きもしてくれない。当然のことだった。

1979年から1983年まで、拠点として使用した杉並区永福町のセンター。いかにも牧歌的な仕分け風景。学生運動くずれとヒッピーくずれが同居していた。
きっかけは灯油ストーブを買う際にローンが組めなかったことだというから、何とも切ない。
結局そのローンは藤本さんの個人名義で組んだそうだが(保証人は加藤登紀子以外に考えられない)、もはや甘っちょろい学生運動とは違う、社会的責任を果たせる事業体として自立させなければならない、という自覚が芽生えたのだ。
フツーなら設立前に議論すべきことだが、成り行きと決意でここまできて、凍えるような事務所で気づかされた“社会と私”……登紀子さんにはたくさんの哀切の歌詞が浮かんだことだろう。
今夜も、やってくるのは、ちょっと疲れた男たち
風の寒さを忍ばせた、背広姿の男たち
ああ、どこかに何かありそうな、そんな気がして
俺はこんな所にいつまでも、いるんじゃないと ~
この曲「時代遅れの酒場」がリリースされたのが1977年10月。これは偶然ではない。
ここからである。
震えながら炎を自家発電させ、熱い議論が始まる。
有機農業に人生をかけた生産者がいて、子を抱きしめながら待ってくれる消費者がいる。
この仕事を途中で放り投げることはできない。持続可能で、社会的に信用される組織に成長させなければならない。
法人化させよう。
最初に候補に挙がったのは生活協同組合だった。
しかし生協とは消費者の組織であり、しかも行政による認可団体のため、事業領域がその行政区内に制限されていた。
広く首都圏に会員が散らばっていて、生産者も会員となって運営する大地を守る会で採用できる形態ではなかった。
活動領域を限定されず自由に活動したかったし、何より行政に縛られたくない。胸の中には設立前に断られたトラウマもあったようだ。
社団法人や財団法人といった形態も検討されたが、その設立要件を満たせる力はなかった。
今ならNPO法人という選択肢があるかもしれないが、当時には存在しなかった。
そこで飛び出したのが「株式会社」という案である。
しかし株式会社とは資本主義社会を体現する営利組織であって、市民運動サイドから見れば、経済効率を追い求める金儲け主義の代名詞のようなものだった。
当時の資本家と労働者の対立は、今日のような生ぬるいものではなかった。
まったくあり得ない選択だと思われたが、しかし議論はそこから発展し揉まれていったのである。(続く)