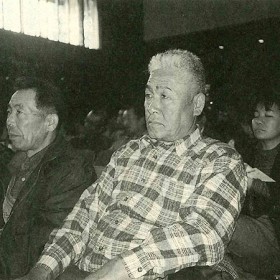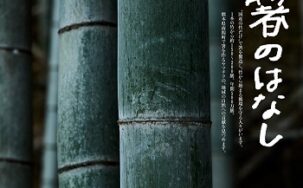1980年前後から、大地を守る会はそのウィングを大きく広げ始める。
牛乳だけでなく、数々の物語が生まれた。人との出会いがあり、新たなモノとテーマによって鍛えられ、ミッションが体系として固まっていった時代である。
大地を守る会の歴史に青空市が欠かせないように、この物語も青空市から始まる。
1978年のとある日(としか書けない)、江東区の団地主催で行われた青空市で、牛肉を販売するオジサンと隣り合わせになった。五島(ごしま)和七さん、当時60歳。
日本短角種という聞き慣れない和牛を世に出すために、宮城県鳴瀬町から移動販売車を一人で運転し、各地で牛肉を販売して歩いていた。
当時「大地を守る会食肉部」という部署があって、埼玉・入間黒豚振興会や山形・米沢郷牧場からの豚肉や牛肉の販売を始めてはいたが、畜産との関わり方はまだ模索段階だった。
食肉部のスタッフとして働いていた道場公基・室井好文の二人は、ここで五島さんから日本短角種について教えられることになる。
日本短角種。
古くから東北地方で荷役牛として育てられていた南部赤牛(祖先は蒙古・韃靼・ロシアといった説がある)に、明治4年、アメリカから導入されたショートホーン(短角)種が交配されて誕生した。東北北部に点在する短角牛を「日本短角種」として公式に呼ぶようになるのは戦後になってからである。
東北北部の山間地で育てられてきた、厳しい冬の自然にも耐える強健な牛。
5月から10月までは山に放され、冬は里に下ろして牧舎で育てる「夏山冬里方式」という飼育方法に、選抜されたオス牛をメス牛群に放して自然交配させる「まき牛」繁殖という独特の生産方式が守られてきた。
性格は大人しく、病気に強い。乳の出がよく、母は夏の間、自力で仔牛を育てる。
自然飼育のため肉は赤身で、臭みがなく、旨い。牛肉本来の味というべきか。しかし脂肪が交雑する“霜降り”にはならないため、市場での価値は低かった。
五島さんはその短角牛の価値を伝えるために奔走していたのだ。
草や粗飼料で育つ、自然環境に適応した畜産の世界がそこにあった。
道場・室井コンビは、生産団体や研究者の集まりであった「日本短角種研究会」にも参加するようになり、「短角こそ俺たちが取り組むべき牛肉だ」と確信する。
そして翌79年、秋田県大湯温泉で開かれた研究会で、道場さんは岩手県畜産課長だった村田敦胤(あつたね)さんから別室に呼ばれ、岩手県山形村(現:久慈市山形町)との提携を要請される。しかもその内容は「山形村を丸ごと引き受けてくれ」というものだった。
短角牛だけでなく、村で生産される野菜や山菜などひっくるめて付き合ってほしい。
当然のことながら、村ごと抱える力など当時の大地を守る会にはなかった。
道場&室井という学生運動時代からの任侠コンビでなかったら、この話はここまで、だっただろう。しかし道場さんはその場で答えたのだった。
「分かりました。やりましょう」
生産物を欲しいだけ契約するのでなく、地域の発展そのものにとことん付き合う。気概以上に、責任の重さに震えたに違いない。
そんな“男の覚悟”など関係なく、いっぽうの村の中は喧々囂々(けんけんごうごう)の騒ぎとなる。
「どこの馬の骨かわかんねえ団体と付き合って大丈夫か」ということだ。
村をまとめ上げたのもまた、“腹を決めた”リーダーたちだった。
このへんの経過は、元村長・小笠原寛さんと小松光一さん(大地を守る会顧問)の共著である『山間地農村の産直革命』(農文協刊)に描かれているので、譲りたい。
1980年12月、陸中農協を介して、いよいよ短角牛の取引が開始されることになる。
初出荷は3頭からだった。(続く)