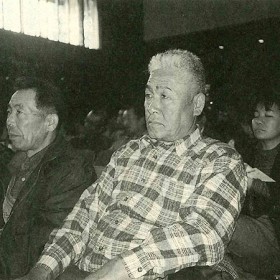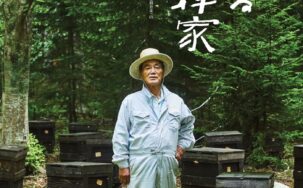高倉凞景医師と「医農学会」に集まる農民との出会いは、取材ではすまなかった。有機農業での野菜作りに挑む生産者の悩みは、栽培技術とは別なところにあったのだ。それは「理解して食べてくれる人」の不在、である。
農薬や化学肥料に頼らず、土壌の栄養バランスを整えて育てた野菜の味には自信がある(僕らはそれを「美味い」というより、「野菜本来の味がする」と表現した)。しかし少しでも虫食いの野菜が混じっただけで市場価値は下がる。いや、「受け入れてくれない」のだ。当時、野菜の売り場は“街の八百屋さん”から大型スーパーに変わりつつあった。時代は、流通の求める規格(サイズなど)に合った野菜が“美しく棚に陳列される”ことを求めるようになっていた。“食べる人の健康”は流通・販売者の視野にはなかった。当然、食べる人の顔など生産者に見えるはずもない。消費者はきれいな野菜を求めている。農薬は必要悪だ。そう自らを納得させて、自身や共に働く妻の健康を損ねる農民たちがいた。
「虫食いでも、安全性と味の良さを知って買ってくれる消費者がいれば、誰だって農薬なんか撒きたくないさ」「やっぱ有機じゃ食っていけない」……
藤田和芳(現社長)の人生を変え、大地を守る会を誕生させたひと言が、ここで飛び出すのである-「私に任せてくれませんか」。
それは軽い気持ちでの安請け合いだった。学生時代からの友人で生活協同組合に勤める者がいて、生協ならこの人たちの野菜を扱ってくれるだろうという読みが働いたのだ。しかしその期待はあっけなく崩れることになる。答えはこうだった。
「生協とは消費者の生活防衛のために“より良いものをより安く”が使命です。市場より高く、しかも天候次第で欠品になる可能性があるなんて、とても扱えない。」
藤田は諦めきれずに都内の生協を回るのだが、結果は同じだった。今でこそ生協でも有機野菜は当たり前のように扱われているし、遺伝子組み換えや脱原発・TPPなどでは運動を共にする仲間だけど、1975年当時はそうだったのだ。
団塊世代の負けず嫌いが大地を守る会を生んだと言ってもいいのかもしれない。遅れてきた世代(シラケ世代とも言われた)の僕から見ると、彼らは「ごめんなさい」が言えない人たちだ。この30数年、藤田社長から聞いたのも、せいぜい「それは失礼した」くらいだろうか。いやまあそれはともかく、彼は「お役に立てず…」と謝って逃げることができず、敢然と「じゃあ俺たちで売って見せる」と答えたのだ。生協陣営に対する対抗心もきっと芽生えていたんだろう。
地方から出てきた若者が、学生運動に飲み込まれ、社会改革の夢を捨てきれずに悶々とした日々を送っていた時に出会った有機農業。火が付いたのだろうか。野菜をトラックに積んで、向かったのは江東区大島4丁目団地。空き地に野菜を並べて訴えた。
「〇〇さんが作った無農薬の野菜です。食べてみてください!」
かつてヘルメットをかぶって革命を叫んでいたエリート学生が今は落ちぶれて団地で野菜を売っている、と週刊誌で嘲笑された。そんな時代だった。
とにかく手に取ってもらう、食べてもらう、たたかいはそこからだ。その意味で「青空市」は大地を守る会の運動と事業の原点だと、僕は今でも思っている。