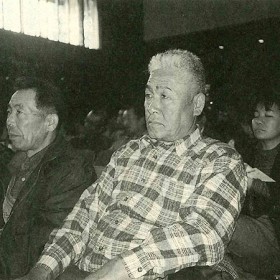83年夏から始まった大地を守る会と山形村との交流は年を追って活発になり、村の空気も変えていった。
田舎(いなか)と言われる場所に住んでいると、ともすると都会の生活様式との落差に劣等感を抱いてしまう。しかしそれはけっして“貧しい”ということではない。
モノにあふれ、ライフラインの便利さを享受する都会でも、一方で何か大切なものを置き去りしてきたような喪失感を抱くことがある。本物の豊かさとは、守るべきものは何か、そんなことを考えるきっかけづくりこそ、都会と田舎の交流の醍醐味だと思う。
「星がいっぱいで、とってもきれいだった」
「水も空気もぜんぜんちがう。友だちに山形村を見せたい」
こんな感想文を子どもたちが書けば、大人たちは「ただ食べるだけでいいのか」と自問自答し始めたりする。しかし食べることとは、「守り合う」関係を築くことである。これはどんな支援よりも強い。なぜなら、食うことは“命がけの行為”だから。食べることで「つながる」、ここに食の持つ大きな力がある。
その関係が疎外され、いのちの値段が軽くなり、自然も健康もお金で奪い合うような時代になって、大地を守る会は生まれた。そして「食の安全」から「交流」の意味を学んだ。
しかもただ親睦を深めるだけでない、その価値を劣化させることなく持続させることの大切さ。それを教えてくれたのが「山形村交流ツアー」だったと僕は思っている。
自分の生産物に自信や誇りが生まれることで、それを育む自然環境や風土にも愛着が生まれてくる。いや元々あった愛着を覚醒させるのが「誇り」なのかもしれない。
動いた一人が、短角牛肥育の指導者、木藤古(きとうご)徳一郎さんだった。
山形村内でも“貧乏村”と呼ばれていた木藤古集落に消費者を招いた。そこにはバッタリーと呼ばれる人力(あるいは水車の力)で穀物をつく搗精機があった。
美しくも厳しい大自然、貧しいと思っていたら“なんと豊かな”と感動された食材群(それを日本人は幸とも恵みとも呼んできた)、それらを暮らしに活かすマンパワーと生きた道具。
第1回のツアーで泊まった歌手の加藤登紀子さんが「木藤古さん幸せだなあ」と漏らしたことで、徳一郎さんの心に火が点いた。
二年後の1985年、徳一郎さんは木藤古集落を「バッタリー村」と名付ける。もちろん公式地名ではないが、以後バッタリー村は都市との交流拠点となる。今でも研修に訪れる若者が後を絶たない。
その後、大地を守る会での山形村短角牛の取引頭数は順調に伸びていった。
輸入穀物に頼らない(2006年には国産飼料100%を実現させた)自然放牧の赤身肉は、いつしか料理人の世界でも評判を呼び始め、今では和洋問わず著名なシェフたちの間で「自慢の牛肉」として紹介されるまでになった。
2006年に合併して久慈市山形町になったとき、何とか村の名を残したいと「いわて山形村短角牛」を商標として登録した。「村」を誇る強い気持ちが表れた行動だった。
その誇りをもって「山形村の短角」は立派なブランドとなった。
しかし短角牛の未来はけっして明るいものになってはいない。
1986年をピークに飼養頭数は減少し始める。生産者の高齢化に加え、91年の牛肉自由化も追い打ちをかける格好となった。
また山形村内でも、大地を守る会に依存するばかりでなく、村として自立できる経営体質を育てていく必要があるという議論が生まれていた。
村の力で産業振興をはかっていこう。短角牛や村の特産素材を使った加工品や惣菜の開発、首都圏だけでなく東北での販路開拓などが話し合われた。
そして数年かけた議論ののち、1994年1月、村・農協・大地を守る会の出資による第3セクターの食品加工会社「総合農舎山形村」が誕生することとなる。(続く)