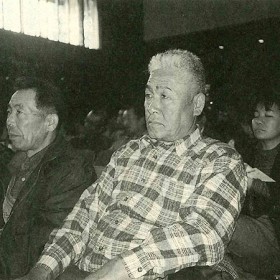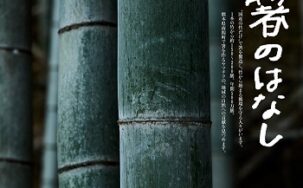大地を守る会の歴史を一本の川として、その源を遡っていくと一人のお医者さんにたどりつく。医師の名は高倉凞景(ひろかげ)、医学博士で元陸軍軍医。当時出版社に勤めていた藤田和芳と高倉医師の出会いがなかったら「大地を守る会」は誕生しなかった。時代の流れから似たような団体は生まれたかもしれないが、それは別な場所、別な形の川になる。
きっかけは『サンデー毎日』1974年7月28日号。「毒ガス研究から出た肥料~」という記事が藤田の目にとまり、茨城の水戸まで取材に出向いたのが事の始まりである。
高倉博士は1936年、23歳で入隊し、陸軍病院の化学兵器研究局に勤務した。与えられた任務は毒ガス兵器の研究だった。その後満州で敗戦を迎え、1946年12月、引き揚げてきた博多港で博士が目にしたのは、人々に吹きかけられる白い粉、有機塩素系の殺虫剤DDTである。それは博士が研究した毒ガスの原料に他ならなかった。「やがて神経外科の患者が増えてくる」と博士は予感した。
郷里の茨城に戻って開業した博士のもとに、1950年頃から、かつて研究した毒ガス中毒と同じ症状を訴える患者がやってくるようになった。その多くは農民だった。博士は診療しながら、農薬に依存しない農業を考え始める。ただ危険性を訴えるだけでは農民は救えないと考えたのだ。
しかしその後の道のりは険しかった。農薬を使うなと説いて回り、農業の研究に没頭する医者を周囲は変人扱いし、「きちがい博士※」とまで嘲笑された。しかし博士はやがてミネラル(マグネシウムや鉄など作物の生育に欠かせない微量要素)の重要性に気づき、新しいミネラル肥料を開発する。理解者も増え始め、仲間とともに「国際医農学会」を設立。藤田が訪ねたのはその頃だった。そこで無農薬での野菜作りに挑戦する生産者たちに出会うのだ。そして彼らの苦闘に巻き込まれていくことになる。
※当時の表現をそのまま再現。
原爆の平和利用が原発なら、毒ガスの平和利用は農薬である。もちろんすべてを否定するものではない。食糧増産に貢献した側面もあるだろう。今は低毒性で選択性の農薬開発も進んできている。しかし虫や菌を殺し、人の体や生態系バランスを狂わせるものである以上、そのリスクは正確に理解されなければならない。「規定通り使えば安全」だと農薬メーカーは言うが、本来は「こういうリスクがあるから適切に管理し、慎重に扱うように」と指導すべきものである。普及後に新たな危険性が証明されて消える農薬も多い。DDTもそうだ。
ちなみにDDTは、第二次大戦中、日本から除虫菊の輸入が途絶えた米国で実用化された。戦後日本に持ち込まれ、シラミ対策や農薬として大量に使用された。その後危険性が指摘されるようになり、1971年に農薬登録が失効、81年に輸入も製造も禁止された。殺虫性を発見したスイスの科学者、パウル・ヘルマン・ミュラーは1948年、ノーベル生理学・医学賞を受賞している。毎日食べる野菜の裏にも、光と影の歴史がある。