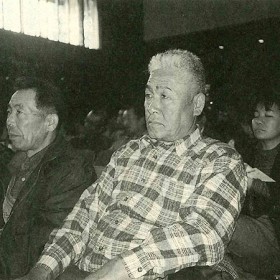ここで改めて、米(コメ)を通して、大地を守る会の歴史をたどってみたい。
これまで牛乳や牛肉や魚を素材として、大地を守る会の理念や手法が形成された経過を抽出してみたけれど、コメもまた、いやコメこそ、この組織の生き方がもっとも色濃く反映された素材だと思うのである。
日本農業の基幹作物であり、消費が減ったとはいえ、やはり主食だし。
1970年代は有機農業運動の勃興期で(といっても新しい農業ではない。農薬と化学肥料に依存した近代農業に対する批判・代替案として「有機農業」という言葉が生まれたが、人類の歴史において農業の土台はつねに有機農業であり、自然を利用した様々な技術や材料を化学合成物や薬物に置き換えて、効率を追い求めたのが「近代農業」である)、当然のごとく主食であるコメについても、有機農業(無農薬・無化学肥料栽培)への挑戦が各地で生まれた。
大地を守る会も有機農業に挑む野菜や茶農家との出会いから始まり、コメでも有機農家とのつながりが生まれるのだが、しかしコメの販売には大きな壁が立ちはだかっていた。
「食糧管理法」(以下、食管法あるいは食管制度)という法律が存在していたのだ。
コメの流通は麦とともに国家統制のもとにあり、農家と直接売買するコメは「ヤミ米」と呼ばれ、処罰の対象とされた(実際には相当量がすでに出回っていたのだが)。
主食であるコメの需給調整と価格安定のために、コメは全量政府の統制下に置く。
それが食管制度の目的で、農家からは高く買って生産の安定を図り(生産者米価)、民間には安く売り渡して(消費者米価)、消費生活の安定を図った。
この制度の源は大正時代の米騒動にまで遡る。
食管制度は戦後の食糧難を乗り切るのに大きな役割を果たした。生産量は飛躍的に伸びて国民生活は安定していった。
しかし一方、コメの価格差は逆ザヤとなって国の負担も増大し、60年代後半には「食管赤字」と言われた財政負担は年間1兆円にまで膨らんでいた。
そこで政府は消費者ニーズの高いコメは価格統制から外し、市場機能にゆだねる「自主流通米制度」を導入すると同時に、生産調整を開始する。いわゆる「減反政策」である。1969年のことだ。
以後、人類史上例のない、国が食料の生産を減らすという政策が長く続くことになる。
大地守る会が設立されたのが1975年。その数年後には(正確な記録が残ってない)、コメをどう流通させるかの模索が始まっている。最初に取り組んだ相手は、秋田県大曲市の大曲有機農業研究会だった。
自主流通米が広がっているとはいえ、それも食管制度の管理下のことであって、販売は国から免許を与えられた業者に限られていたし、販売者の販売エリアも隣接する自治体までという制限があった。何より農家にとって、制度外の流通に手を貸すことは、地域(実際は農協)を敵に回す恥ずべき所業とされていた。
小さな共同購入団体のなかには農家との直接取引(ヤミ米産直と言われた)を行なうグループもあったが、法人組織にできることではなかった。
特定の生産者のコメを特定の消費者に届ける仕組みがないなかで、いったい誰が考えたんだろう(藤本敏夫か藤田和芳以外にいないと思うが)、こんなワザが編み出されたのだ。
まず、基本は「自主流通米制度」に則って行なう。生産者は正規の集荷業者に売り、指定の販売業者に卸してもらう(実際は伝票だけ通してモノは直接届ける)。
販売業者は、当時から有機米の流通に積極的だった八王子の ㈱マゴメさん。しかしマゴメさんから大地を守る会経由で首都圏に広がる会員に販売することはご法度である。
そこで八王子に隣接する日野市に「日野大地と命を守る会」という怪しげな団体を立ち上げ、そこにまとめて卸してもらうことにした。
会員は「日野大地~」に米を注文し(消費者の買い先は自由だから)、「日野大地~」は ㈱大地(当時)に配達を委託する。㈱大地は配達手数料をいただくだけ。
会員には通常の注文書とは別に「日野大地と命を守る会」宛てのコメの注文書が配られた。『配達は ㈱大地に委託します』の一文つきで。
この方式は食管法が廃止される1995年まで続いた。
この手法はコンプライアンス(法令遵守)的にはグレーな部分を残しつつも、食糧庁(当時)から訴えられることもなく、僕らは生産者の“顔が見えるお米”を届ける道筋を編み出し、堂々と広げていった。以後少しずつ生産者も増えていった。
その間も減反政策は続けられ、耕作放棄地が目立つようになり、農業者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっていった。米は自由に流通(=競争)されるようになり、食管制度の形骸化は誰の目にも明らかとなっていった。
そして1986年、降って湧いたようにアメリカから市場開放要求がつきつけられた。
大地を守る会の真価が問われる時代に入った、と思った年だった。