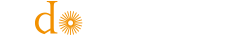あるとき、いくら野菜を作っても、全く良いものができないときが訪れました。一生懸命やっているのに、なぜか。その人は立ち止まって栽培を見直します。埼玉県川越市で農業を営む吉澤重造(じゅうぞう)さん、御年81歳の土作り。
採れなくなって気が付いた
青く豊かに茂った大根の葉に朝露のしずくが光り、その上をたくさんのモンシロチョウが飛び交っています。9月初めに種を播いて、収穫を控えた10月終わりの畑です。
今回私たちが訪ねたのは、埼玉県川越市で代々続く農家の10代目、吉澤重造さん。妻のとみ子さん、長男の重幸さんとともに、農薬・化学肥料に頼らず野菜を育てています。


大地を守る会に農産物を初めて出荷したのが1981年というベテラン生産者ですが、遡ると一般的な慣行栽培を行っていた時期があるといいます。当時はまだ、「量が採れればいい」という時代でした。
「昔は農薬も化学肥料も使ってた。そしたらあるとき、ぱたっといいのが採れなくなったんだよ。大根採って市場に持ってくでしょ。極端な話だけど翌朝には傷んでる。そしたらある人に、あなたの作り方は間違ってるっていわれてね」と重造さん。
「間違ってる」と説いたのは当時知り合った果物商でした。その人がいうことには、「大根は曲がりたい、腐りたいなんて思ってない。肥料をたくさん入れて弱らせてるのは農家の人たち」。人間の体でいえば食べさせすぎということ。健康な野菜を作りなさいと諭されたそうです。
事実、生気がない大根の姿を目の当たりにしていた重造さんは、その声を無視することができません。恐る恐る化学肥料を使わず育ててみます。するとどうでしょう。立派な大根ができました。「量をたくさん」「形を太く」と疑いなく使ってきた化学肥料がなくても、見た目が良く、中身も元気な大根ができたのです。
ここから重造さんは野菜の作り方を根本から見直します。農薬・化学肥料に頼らない栽培の始まりでした。

「さらさらでにおいも何もしないでしょ。ほら」。この日、重造さんは畑に使っている自家製たい肥を見せてくれました。5年が経過したたい肥は乾いた感触で色は深い黒。確かににおいはありません。材料は山林を伐採した際に出る枝や根を造園関係業者が砕いてくれたもの、そして養鶏業者が譲ってくれた鶏糞です。
「1年もたたないうちに畑に入れたらまだ生の状態。においがするのは未熟だからだよ。微生物がたい肥を分解して、これならいいと仕上がったのを入れなきゃ畑はだめだ」。
未熟な状態で畑に入れると生育障害など、かえって良くない作用を及ぼします。一方、重造さんが作るたい肥は、完成まで最低でも2年。切り返しと呼ばれる、混ぜる作業の過程で酸素に触れさせ分解を促します。

小さな存在に生かされている
でき上がったたい肥は、畑の貴重な栄養分。畑に撒いて、耕しながら鋤き込んでいきます。たとえば大根の場合、「大根十耕(だいこんじっこう)」といわれ、先端が当たらない深さまでよく耕すことが大切。土の中でまっすぐ下に伸びて生長できるよう、70㎝の深さに届く耕運機でやわらかく耕し、たい肥を入れるのです。
私たちの目には見えませんが、土の中には、たくさんの小さな命、微生物が存在しています。たい肥に含まれる有機物は、畑の微生物の餌となるとともに、たい肥自体に含まれる微生物によって多様な命が共存するバランスが取れた土壌を作ります。重造さんは人間の体にたとえます。
「土の状態は人間の腸の状態と同じなんだよ。土の中の微生物のバランスが整うのと、人間の腸の中の菌のバランスが整うのは一緒。整えばどちらも健康、良い状態になる」。
農薬や化学肥料に頼らない栽培の場合、こうした微生物の力を借りて、土の力を高めることが基盤となります。健康な土は病気を寄せ付けず、元気に育った野菜は虫を遠ざけ、農薬に頼ることなく生長できるのです。

葉が枯れて収穫を告げる
重造さんの里芋畑では、直立すると2mにもなる背の高い葉が、くたっと地面に横たわっていました。
「お盆過ぎたらもう葉っぱの生長はいらないの。葉っぱを作ること考えてたら、芋を太らすこと考えられないでしょ。芋が太って、私の役目はおしまいよって、こうなったらいい」。
芋が十分生長すると、葉が枯れて収穫を知らせてくれるといいます。

里芋は、畑に植えた種芋が親芋として生長し、その周りを囲むように、子芋ができます。同じように子芋の周りに孫芋ができ、孫芋の周りにひ孫芋ができることもあります。
里芋の株を掘り起こす収穫作業を見ていると、ごろんごろんと巨大な塊が土の中から出てきました。
30㎝ほどの親芋に子・孫芋が付いて、根がひげのようにぶら下がっています。泥を纏って10㎏はあろうかという迫力。この塊を地面にどーんと落としてばらしてから、子と孫を手でぽきぽき外していきます。ここでようやく、よく見る里芋に近付きました。
通常出荷されるのは、孫芋。1つの子芋から、大きい孫芋が3つ4つ採れるのが理想ですが、当然思うように形はそろいません。けれども、「これが自然なんだからいいんだよ」と重造さん。「工業製品は1㎜の狂いもなく仕上がるけど、生き物はそうはいかない。いろいろな形でも面白いと理解してもらえるといいね」。




里芋の出荷仕事は人の手による作業の連続です。ごつごつした里芋を洗ってむくのが面倒だと思うことがありますが、産地ではそれ以上に手間がかけられていると知りました。
土の健康を土台にした重造さんの野菜作り。農薬に頼る代わりに、雑草は2〜3㎝伸びたところで土をかぶせて抑え、新芽に幼虫を見つけたら手で捕ってしのぎます。それでも虫に食べられてしまったら「採れただけありがたい」と受け止める。そこには「農業は天候に左右されるものだから」と自然にならう、謙虚でおおらかな姿がありました。
「畑に種落っことすのと、魂込めて播くのじゃ違うよ」と、丹精込めて土から作った野菜を、私たちは感謝の気持ちでいただきたいと思います。


大地を守る会の野菜はこちら
※該当商品の取り扱いが無い場合があります。