2012年9月29日
原田正純さんをしのぶ会
「お前の原点は何だ?」 と聞かれたら、ま、何の原点かにもよるけど、
「社会」 というものに目を開かされた原点となると、
やっぱり 「水俣病」 と言わざるを得ない。
僕の人生は水俣病発見からの時間に等しく (公式発見は生後5ヵ月の時)、
魚貝の生命を頂戴しながらつくってきたような体を持つ身にとって、
「ミナマタ」 は呑気な少年の脳天を直撃した、衝撃の事件だった。
大人向けのドキュメンタリー番組にくぎ付けになって、
松田優作ふうに言えば、「なんじゃ、こりゃあ!」 である。
その水俣病に対して 「見てしまった責任」 を全うした医師がいた。
水俣病研究の第一人者、6月に亡くなられた原田正純先生
(熊本大学医学部助教授~熊本学園大学教授・水俣学研究センター長)、
享年77歳。
今日、その原田さんをしのぶ追悼講演会が開かれたので、
雑事は後回しにして参加した。
場所は有楽町マリオンにある朝日ホール。
遺影の前に献花台が設けられていて、
花を一輪供えて、御礼を申し上げることができた。
この機会を与えてくれた主催者、NPO法人「水俣フォーラム」 に感謝したい。
講演会では、7人の方のお話と
欠席されたお一人からのメッセージが読み上げられた。
宮崎市にある潤和会記念病院院長の鶴田和仁さん。
「 原田さんの功績は、何と言っても胎児性水俣病の発見にあるが、
有機水銀が胎盤を通るなどということが当時の医学ではあり得ないと言われていた時代に、
奥さんが病院から持ち帰ったへその緒を見て臍帯の調査を思い立ち、そして立証した。
その道筋 にこそ原田さんのすごさがある。」
「 原田さんは後継者を探していたが、
" 原田さんの前に原田なし、原田さんの後に原田なし " と言うしかない。
常に患者さんから学び、水俣病の悲劇を伝えることに心血を注いだ伝道師。
まさに時代が必要とした人だった。」
患者運動のリーダーだった故川本輝夫さんのご長男、川本愛一郎さん。
「 父・輝夫は13年前、67歳で死亡しました。
私は1958年、水俣病の爆心地とも言える月の浦で生まれました。
子どもの頃から父と原田先生はいつも一緒にたたかっていて、
親父は原田先生を 「戦友」 と呼んでいました。
" 水俣病の本質はすべての人にかかる問題である "
" 特徴的な症状だけで選別できるものではない " とよく言っておられました。」
「 国は " 救済 " というが、 " 償い " というべきではないか。」
映画 「水俣」 シリーズのプロデューサー、高木隆太郎さん。
「 私は40年前から20年間にわたって水俣の映画を作り続けてきた。
命がけで作ってきましたが、原田さんの医学観・科学観は映画作りのベースになった。
彼は 「科学的に立証されてない」 という考えに対して独自の見解を持っていた。
累々たる臨床、フィールドワークで培われた医学思想が、一挙手一投足から感じられた。」
ノンフィクション作家の柳田邦男さんは、東北復興のイベントがあり欠席。
メッセージを寄せてくれた。
「 原田さんはよく 「見てしまった責任」 ということを言っておられた。
病院で診るのではなく、患者さんの家庭を訪ね、その生活の場で見てしまったこと、
つまり現場が彼の生き方を変えた。」
「 科学的定説とは、それまでの経験から割り出された仮説でしかない。
水俣病は鏡である。 ・・・・・
原田先生は永遠です。 その笑顔がいつも私たちの傍にあるのです。」
立教大学名誉教授、栗原彬さん。
「 病気を治すことはできない。 しかし患者さんにとって原田さんは必要な人であった。
原田さんはいつも患者さんのほとりに立っていて、
原田さんが傍らにいるだけで、患者さんの目に輝きが蘇ってくる。
人間性を引き出し、取り戻してくる。
人間にとっての立ち方を教えてくれた人。」
「 川本輝夫さんが叫んだ言葉 - " 人間として謝れ!" 。
近代がつくりだした文明や人間を顧み、
改めて近代をつくり直す作業を、私たちは進めなければならない。」
原田さんの最後の対談に立ち会った朝日新聞熊本総局記者、外尾誠さん。
「 原田さん生前の最後の企画となった15人との対談は、『ことづて』 と題して連載中です。
いつもご自宅で行ないましたが、とても居心地の良いお宅で、
原田さんはいつも私たちを気遣い、ユーモアやウィットで和ませてくれました。
とてもカッコイイ人でした。」
連載中の記事は残念ながら九州と山口県でしか読めないが、
原田さんとは出版する約束をしたとのこと。
経済評論家の佐高信さん。
「 原田さんは、いつもニコニコしていた。
しかしその裏には、権威や御用学者に対する凄まじいまでの怒りが渦巻いていた。」
「 原田さんは " 患者さんだけにしたらいかんよ " と言い残されている。
それぞれがそれぞれの形で引き継いでいく、そのための備えをしなければならない。
11月から始まる 『水俣病大学』 は、その一つの形としてスタートする。」
見てしまった者としての責任、知ってしまった者としての責任、、、
言うのは簡単だが、全うするのは容易なことではない。
3.11と原発事故を経験して、私たちはより厳しく、
次代に向けての 「人間としての立ち方」 が問われているように思う。
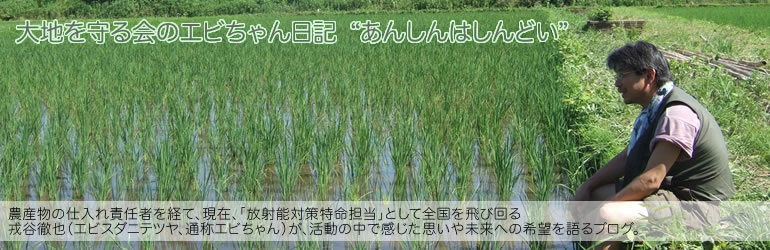
いま、「この道を・・水俣から」を読み進めています。渡辺さんや浜本二徳さんのやさしさをおもいます。日吉さんは老人ホームにいらっしゃるとのことですが、何とかお伺いしたいと願っています。